- 糖尿病内科を受診希望の方は以下の持ち物をお忘れないようご来院ください
- 鶴見近くの糖尿病内科
- 糖尿病とは
- このような症状はすぐにご相談ください
- 糖尿病内科で行う検査
- 当院の治療方針
- 糖尿病に伴う合併症の評価を行います
- 検査結果は、便利なオンライン診療で
糖尿病内科を受診希望の方は
以下の持ち物をお忘れないようご来院ください
- 健康保険証(有効期限を確認する)
- 各種医療受給者証(お持ちの方)
- 紹介状(お持ちの方)
- お薬手帳(お持ちの方)
- 健康診断などの結果表(お持ちの方)
- 糖尿病連携手帳(お持ちの方)
- 血糖測定器(お持ちの方)
- 他医療機関で受けられた検査結果や人間ドッグの結果
(お持ちの方)
鶴見近くの糖尿病内科
 糖尿病内科は、糖尿病を発症した方、また血糖値が高く糖尿病を発症するリスクのある方を対象に診療を行う診療科です。糖尿病は、血糖値が高い状態が続くことで血管に負担がかかって動脈硬化が進行することで、神経、目、腎臓の順に悪くなっていきます。他にも脳梗塞や心筋梗塞の原因の一つになります。
糖尿病内科は、糖尿病を発症した方、また血糖値が高く糖尿病を発症するリスクのある方を対象に診療を行う診療科です。糖尿病は、血糖値が高い状態が続くことで血管に負担がかかって動脈硬化が進行することで、神経、目、腎臓の順に悪くなっていきます。他にも脳梗塞や心筋梗塞の原因の一つになります。
当院では、当日中にHbA1cを測定できる検査機器を準備しており、患者さんそれぞれの糖尿病の種類に合わせた治療を行っていますので、いつでもお気軽にご相談ください。
糖尿病とは
 膵臓から分泌されるインスリンは、血液中の糖を細胞に取り込み、血糖値を下げる役割を持つホルモンです。しかし、その働きが低下し、血糖値を下げることができなくなると、血管に炎症が起こり動脈硬化が進みます。その結果、腎臓や神経の障害、難聴を引き起こすだけでなく、心筋梗塞や脳梗塞といった深刻な疾患の発症リスクも上がります。
膵臓から分泌されるインスリンは、血液中の糖を細胞に取り込み、血糖値を下げる役割を持つホルモンです。しかし、その働きが低下し、血糖値を下げることができなくなると、血管に炎症が起こり動脈硬化が進みます。その結果、腎臓や神経の障害、難聴を引き起こすだけでなく、心筋梗塞や脳梗塞といった深刻な疾患の発症リスクも上がります。
代表的な症状は、疲れやすさや喉の異常な渇きなどがありますが、自覚症状がほとんどないまま、健康診断で発見されるケースも少なくありません。なお、糖尿病には、遺伝的な要素をもつ1型糖尿病と生活習慣病としての2型糖尿病があります。
1型糖尿病
膵臓がインスリンを作れなくなるのが特徴で、自己抗体が原因であることが多いことから比較的若い方に多く見られます。自分でインスリンを出すことができないため、インスリンを補う治療を行い、血糖値を厳密に管理します。
2型糖尿病
遺伝的素因と運動不足、糖質の多い食事、ストレスなどの生活習慣が組み合わさって発症するタイプの糖尿病です。インスリンの分泌が不足したり、インスリンに対する感受性が低下したりすることで発症します。
そのほかのタイプも
日本では、糖尿病患者数の90~95%が2型糖尿病とされています。つまり1型糖尿病は5%以下で、残りは妊娠中に起こる妊娠糖尿病や、薬などが原因で起こるその他の糖尿病と考えられます。
治療方法は糖尿病の種類によって異なる上に、同じ2型糖尿病であっても患者さんの生活習慣や体質によって治療法が変わってきます。当院は母性内科も併設しているため、妊娠糖尿病に対しても柔軟な治療が可能です。
妊娠糖尿病
妊娠中は胎盤から分泌されるホルモンの影響で一時的にインスリンの効きが悪くなり、血糖値の異常が生じることがあります。妊娠中の定期検査で発見された場合に妊娠糖尿病と診断されます。
妊娠前から糖尿病がある場合は糖尿病合併妊娠といわれます。早産や赤ちゃんの成長に関わるため、妊娠を迎える前からの管理が重要となります。
このような症状はすぐに
ご相談ください
糖尿病はそれ自体ではあまり目立った症状を引き起こすことはまれです。多くの場合、静かに進行し、合併症による症状に気づいた時にはすでに重症になっていることも少なくありません。
以下の症状に心当たりのある方は、お早めに当院へご相談ください。
- 急激な体重減少
- 尿意が頻繁になり、トイレに行く回数が増えた
- 辛いものを食べたりしていないのに喉が渇く
- 足首や手などにむくみやしびれがある
- 体全体がだるく疲れやすい
- 立ち上がったときにめまいがする
- 健康診断で血糖値が高いと言われた
HbA1cが高いと診断されたら
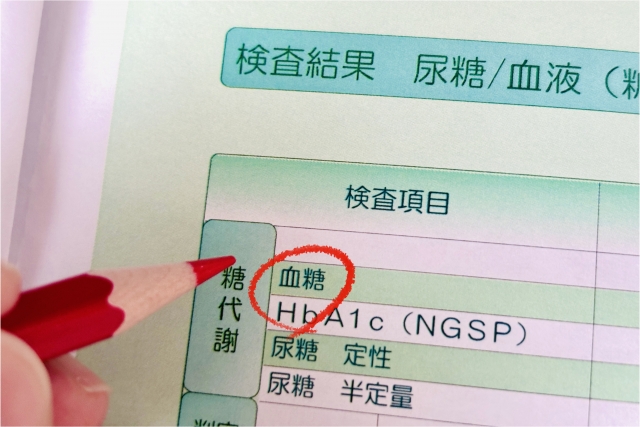 HbA1c(ヘモグロビンA1c)は、糖尿病の状態を調べるために行う検査です。血糖値は運動や食事の影響で短期的に変動するため、HbA1cというヘモグロビンに結合したブドウ糖の割合を調べます。この割合は直近1~2ヶ月の血糖値の平均と連動しているため、HbA1cを調べることで過去1~2ヶ月の血糖値の平均を把握できます。
HbA1c(ヘモグロビンA1c)は、糖尿病の状態を調べるために行う検査です。血糖値は運動や食事の影響で短期的に変動するため、HbA1cというヘモグロビンに結合したブドウ糖の割合を調べます。この割合は直近1~2ヶ月の血糖値の平均と連動しているため、HbA1cを調べることで過去1~2ヶ月の血糖値の平均を把握できます。
診断にはHbA1cと血糖値を合わせて行います。診断に至った場合は食事療法や運動療法で経過をみれるか、即座に治療が必要かの病態を確認することが大切です。HbA1cが7.0%以上で慢性化すると合併症のリスクも高まりますので、早めに適切な治療を開始する必要があります。
糖尿病内科で行う検査
糖尿病の検査には、血液検査と尿検査があり、両方受けることが推奨されます。
糖尿病の血液検査
糖尿病の代表的な血液検査は以下の通りです。
血糖値
血糖値検査は、糖の血中濃度を調べる検査です。
血糖値は食事の前後で変化しますが、空腹時だけでなく食後2時間の血糖値も調べることで、血糖値を下げるホルモンであるインスリンが正常に働いているかどうかがわかります。
HbA1c
HbA1cは、約1~2ヶ月の高血糖の有無や程度を調べる検査です。
また、血糖値を下げる役割を持つホルモン「インスリン」の分泌状態を調べるため、以下の血液検査を追加する場合もあります。
- 血中インスリン
- C-ペプチド
上記の検査は、インスリンの分泌能力やインスリンに対する抵抗性を判断するのに役立ち、治療計画にも大きく影響します。
糖尿病の尿検査(尿中アルブミン)
尿中アルブミンは、糖尿病の合併症である腎機能障害を早期に発見するスクリーニング検査として利用できる検査です。
糖尿病に伴い尿中アルブミンが検出される場合、将来透析が必要になるリスクが高くなりますので、早めにこの検査を一度受けておくことをお勧めします。
糖尿病の治療
当院の治療方針
 糖尿病の治療では、次の3つのポイントを意識することを大切にしています。
糖尿病の治療では、次の3つのポイントを意識することを大切にしています。
- 栄養バランスのとれた食事
- 適切な運動習慣
- 個々の症状に適した薬物療法
当院では、患者さんそれぞれに合った食事や運動のプランを、ライフスタイルや体調に合わせて一緒に考えていきます。
また、薬物療法を行う際には、注射薬や内服薬などを含め、患者さんにとって最適な薬を処方します。
糖尿病に伴う
合併症の評価を行います
糖尿病の初期には、健康診断で尿糖や血糖値が高いと指摘される程度で、明確な自覚症状がないことが多いとされています。この状態を長期間放置すると、慢性的な高血糖状態が全身の血管に負担をかけ、様々な合併症を引き起こすことがあります。
三大合併症
原因は全身の毛細血管に負担がかかることだと考えられていますが、初期には自覚症状がほとんどないため、定期的な健康診断が重要です。
糖尿病神経障害
三大合併症の最初の症状です。手足のしびれや鈍痛などの末梢神経障害の症状は、手足の血行が悪くなることで現れます。悪化すると壊疽を起こし、切断を余儀なくされる場合もあります。
また、胃腸障害、筋萎縮や筋力低下、立ち上がった時のめまい、発汗異常など、様々な自律神経の障害を引き起こすこともあります。
糖尿病網膜症
網膜の血管に生じた何らかの異常が原因で、眼底出血やむくみが生じます。
初期には視力に異常がなく、ほとんどの場合、眼底検査で異常が初めて発見されます。そのため視力に異常がなくても、眼科で定期的に眼底検査を受けることは大切です。早期発見し、早期治療を受けることで失明を未然に防ぐことができます。
日本では緑内障に次いで失明原因の第2位に糖尿病網膜症が挙げられています。
糖尿病性腎症
腎臓は、血液をろ過して不要な老廃物や余分な水分を尿として排出する働きをしています。しかし動脈硬化により腎臓の障害が進むと尿の中にタンパクが漏れ出します。そこで、尿検査でタンパクの漏れを調べ、血液検査で腎機能の状態を確認することで、糖尿病性腎症の有無を調べます。
腎症が進むと腎機能が止まり、腎不全となり人工透析治療が必要となります。人工透析治療が必要となる原因の最も多いものが糖尿病性腎症と言われています。
その他の合併症
その他の合併症としては、心筋梗塞、脳梗塞、感染症、皮膚疾患、下肢動脈硬化症などがあります。
当院では、患者さんの疾患に応じて、心電図、腹部超音波検査、CAVI(血管年齢測定)などを行うことがあります。
