夜になると咳が出やすくなるのはなぜ?
自律神経の働き
 呼吸や体温、免疫などの身体機能は、意思とは無関係に、自律神経によって調整されています。
呼吸や体温、免疫などの身体機能は、意思とは無関係に、自律神経によって調整されています。
自律神経には、体を活発にする交感神経と、体をリラックスさせる副交感神経の2つがあります。この2つの神経がバランスを保ちながら働くことで、私たちの健康は維持されています。
交感神経は、私たちが活動している日中に優位に働きます。一方、副交感神経は、私たちが眠っている夜間に優位に働きます。
夜間に副交感神経が優位になると体がリラックスし、気管支が狭くなります。これにより、咳が出やすくなると考えられています。
気温や湿度の変化
気温が夜から朝方に低くなると、気道が冷気に刺激されることがあります。
また、眠っている間に口が開いていると、喉や口の乾燥を招き、咳が出やすくなります。
異物が気道に侵入しやすい
寝るときに仰向けでいると、喉に粘液や痰が流れ込みやすくなります。また、布団の中のホコリやダニの死骸など、アレルギーの原因となる物質が気道に入りやすくなり、咳を誘発しがちになります。
咳のメカニズム
咳は、気道に異物や刺激物が入り込んだ際に、それらを体外へ排出しようとして自然に発生する生体防御反応です。ウイルスやアレルゲン、胃液など何らかの物質が気道の粘膜を刺激すると、その情報が脳の咳中枢に伝わり、咳が引き起こされます。つらい症状ではありますが、異物や病原体から体を守るために、なくてはならない重要な役割を果たしていると言えます。また、気温や気圧の変化も咳の発生に影響を与えます。気道が過敏な状態にあると、わずかな刺激でも咳が出やすくなります。特に台風時には咳や喘息の症状が悪化するケースが報告されており、咳喘息の方はこうした環境の変化に敏感になりやすいと考えられています。
夜になると咳が出る原因
マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという菌によって引き起こされる感染症です。小さなお子様から大人まで幅広い年齢の方に発症する可能性があります。乾いた咳をはじめとして、症状は多岐にわたります。
インフルエンザ
インフルエンザの症状は、3~5日間の発熱の後、徐々に症状が消えていきますが、熱が下がった後も咳が続く場合があります。
気管支炎
細菌やウイルスに感染して気管支に炎症が起こる疾患で、症状としては咳が長引く、痰がからむといったものがあります。夜中から明け方に咳が悪化するのも特徴です。
咳喘息
咳が長期的に続く喘息です。熱などの症状がなく咳が長引いている場合には、咳喘息を疑う必要があります。
気管支喘息
アレルギーなどが原因で気道に炎症が起こり、狭くなることで、空気の通りが悪くなります。それにより、咳、ゼーゼー、ヒューヒューいう呼吸音(喘鳴)、息切れなどの症状が起こります。
肺炎
熱や鼻の症状(鼻水や鼻づまり)は見られず、咳だけが長引いている場合は、肺炎の可能性があります。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
主にたばこの煙に長期間さらされることで起こる気管支の炎症です。副流煙も原因となるので注意が必要です。咳が長く続き、痰が出る場合は、COPD(慢性閉塞性肺疾患)が疑われます。
百日咳
百日咳菌という細菌に感染することで起こる呼吸器感染症です。咳が3ヶ月(約100日)止まらないことから、百日咳と名付けられました。急性期には抗菌薬が効果的になりますが、時間が経過すると効果は限定的になります。
肺結核
結核菌に感染して起こる感染症で、初期症状は風邪とよく似ています。咳が2週間以上続き、痰が伴う場合は、肺結核を疑う必要があります。
肺癌
咳は肺がんの初期症状でもあります。風邪でもないのに咳が2週間以上続く場合は、早めに当院へご相談ください。
夜になると咳が出る、
止まらない、咳が長引く場合の
治療法と対処法
夜になっても止まらない咳や、咳が長引く場合は、以下の治療法が有効です。また、ご自身でできるセルフケアの方法も併せてご紹介します。
治療方法
 咳を止めるための咳止めや、痰を抑える薬を処方します。
咳を止めるための咳止めや、痰を抑える薬を処方します。
咳がアレルギーによるものの場合には、抗アレルギー薬も考慮するなど、咳が長引く原因によって、適切な治療を行います。
対処法
水分摂取
喉の乾燥を予防し、咳を止めるために、適宜水分を摂るように心がけましょう。
加湿器を設置
部屋が乾燥していると咳が出やすくなるので、加湿器で空気を保湿しましょう。
のど飴をなめる
のど飴やトローチなども、喉の乾燥を予防するのに効果的です。
マスクの着用
マスクを着用することで、喉の乾燥を予防し、咳を抑えることができます。
3週間以上続く咳は
医師に相談を!
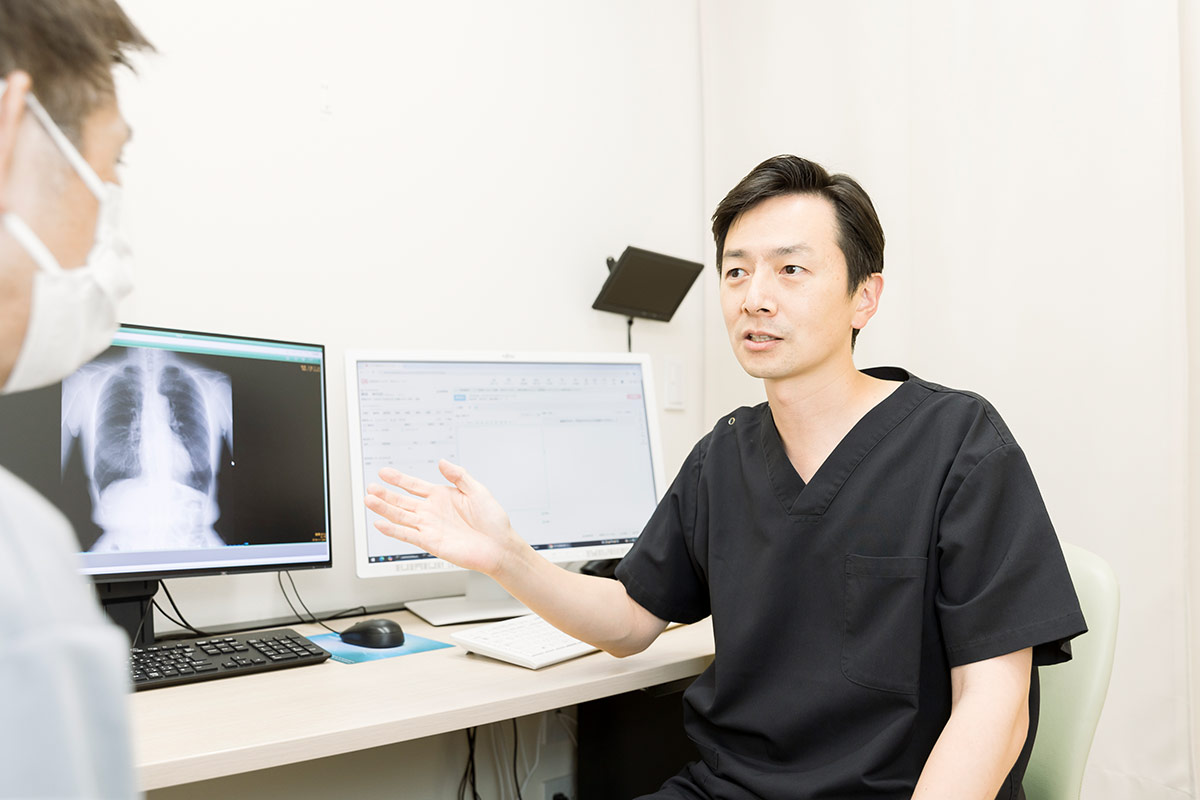 咳がどのくらいの期間にわたって続いているかが、受診のタイミングを決めるポイントとなります。3週間以上続く咳は、風邪以外の疾患が原因である可能性もあります。上述した予防法やセルフケアを試しても咳が止まらない場合や、咳で眠れない、咳に加えて発熱や血痰、色のついた痰、呼吸困難、ゼーゼーという呼吸音(喘鳴)などの症状がある場合は、早めに呼吸器内科を受診しましょう。
咳がどのくらいの期間にわたって続いているかが、受診のタイミングを決めるポイントとなります。3週間以上続く咳は、風邪以外の疾患が原因である可能性もあります。上述した予防法やセルフケアを試しても咳が止まらない場合や、咳で眠れない、咳に加えて発熱や血痰、色のついた痰、呼吸困難、ゼーゼーという呼吸音(喘鳴)などの症状がある場合は、早めに呼吸器内科を受診しましょう。
疾患なのか否か、またどのような疾患であるかによって対処方法も変わってくるため、医師による適切な診断と治療を受けることが重要です。咳が気になる方は、風邪だろうと軽く考えず、症状が続くようであれば早めに受診し、ストレスなく安心して毎日を過ごせるようにしましょう。気になる症状があれば、お気軽に当院へご相談ください。
